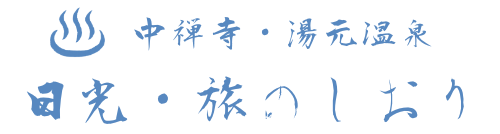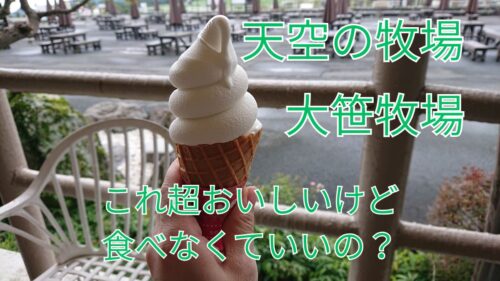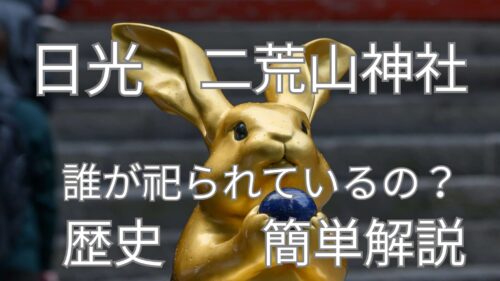輪王寺

世界文化遺産
国の重要文化財
東日本最大級の木造建築物
日光山は勝道上人(しょうどうしょうにん)が766年に開いた山
勝道という名前の僧侶のこと
勝道上人が四本龍寺(しほんりゅうじ)を建てたのが始まり(766年・奈良時代)
日光山輪王寺はお堂や塔、15の支院全体の総称
東照宮よりも800年以上前に建てられた
檀家を持たないため一般のお墓はない
僧侶が日々国の繁栄や安全を祈願している
現在のお堂は徳川家光により再建されたもの(1645年)
平安時代に慈覚大師(じかくだいし)円仁によって建てられ江戸時代に新宮(現二荒山神社)境内に移築
その後家光により正保2年(1645)現在の建物に造り変えられて明治14年に現在地に移築
拝観料400円(三仏像)
本堂(三仏堂)
国の重要文化財
東日本最大級の木造建築
金堂ともいわれる
この中に3体の仏像がある
三仏像
日光の男体山・女峰山・太郎山を神仏化したもの
高さ約7.5m
木造でできていてその上に金箔が貼られている
千手観音(父)男体山
千の手で全ての願いを叶える
阿弥陀如来(母)女峰山
無限の光で守ってくれる
馬頭観音(子)太郎山
頭の上に馬が乗っている
交通安全の御利益がある
昔は馬が交通手段になっていた
三体含めて家族円満の御利益がある
下から見ると目が合うように作られている
江戸時代の平均身長の約155cmで見るとちょうどいい
三仏像を見上げている場所は「修行の谷間」と言われている
我々はここから仏様の世界に上がるまでたくさんの修行を重ねなければならない
悪いことをせずに人のために尽くす
善を尽くすと仏様の世界に行ける
その修行を始める一環の谷間にいるということ
2019年に平成の大修理が完了
約13年かかった
この場所で修理ができなかったので仏像・台座・土台を分けて外へ出した
関東に修理できる人がいなかったので京都まで運んだ
すべて一度に修理に出すと日光に神様がいなくなってしまうので千手観音が先に修理に行った
千手観音が帰ってきてから馬頭観音が修理に行った
阿弥陀如来は京都から仏師に来てもらい修理した
修理に関わった人数は1万人以上
本堂の上にある緑のやつは畳6畳分
三体の仏像がある上の丸い仏様が東照三女権言という
中央 阿弥陀如来
左 釈迦如来
右 薬師如来
相輪塔(そうりんとう)
輪王寺のうしろにある黒と金の塔
天海大僧正(てんかいだいそうじょう)が国の平和と人々の幸せを願って建てた
日光山の聖域を守護していると言われている
147年ぶりに改修された
天海大僧正は家康・秀忠・家光に仕えた徳川幕府のアドバイザーとして有名
だから神橋の前に天海大僧正の像がある
豆知識
おさすりあみだがある(痛いところをさすると治る)
天海大僧正
徳川家康~家光に側近として仕えた僧侶
天海大僧正は明智光秀ではないかという話もある
いろは坂の上に「明智平」という場所がある
日光の見晴らしのいい場所に名前をつけてもらったのか
それとも自分でつけたのか
ただの偶然なのか
念珠
僧侶が祈祷して念仏を込めた数珠が売っている
お通夜やお葬式の会場に入る前に左手ににぎる
玉を上にして房をにぎる
会場入るとき、出るときに悪いものがよりつかないようにするため
お寺に行くときに持っていくとパワーが込められて身を守ることができる